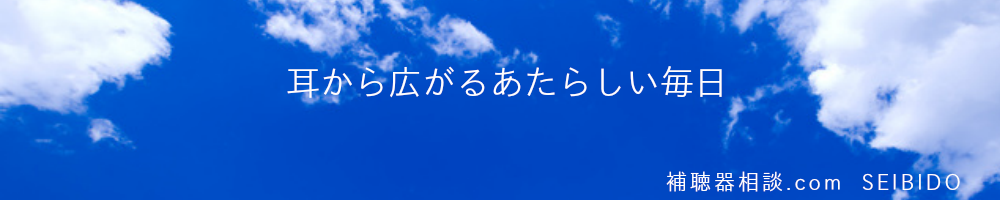「高音」から聞こえにくくなる
前出の「モスキート音」のように、「不快な音」が聞こえないというのはむしろ自分とっては好都合なことです。
ですが、年齢とともに「聞こえない音」の音域は少しずつ広がっていき「日常に必要な音」も聞こえづらくなっていきます。
一般的には、「高い音」から聞こえにくくなります。
「キッチンタイマー」のピピピ・・・という電子音、小さな子供の甲高い声、ピチュピチュという小鳥のさえずり
など、日常における音の一部が少しずつ 聞こえにくくなっていく・・・という感じです。
お孫さんの話が聞きづらい、「キッチンタイマー」が鳴っていても気づかずお鍋を焦がしてしまった、
沸騰したヤカンが鳴る笛音に気付かない、山へ散策に行っても「鳥のさえずり」が聞こえなかった など
今までの楽しみや日常生活に支障が出てくるかもしれません。
子音の聞き分け が出来にくくなる
「あ・い・う・え・お」の音「母音」に比べると 「子音」は周波数が高くなり、聞き分けにくい音になります。
例えば 会話の中で、
石(いし) が 西(にし) に聞こえたり、 魚(さかな) が 高菜(たかな) に
寿司(すし) が 牛(うし) に 笑う(わらう) が 洗う(あらう)に 聞こえてしまいます。
また、 人の名前 佐藤(さとう)さん が 加藤(かとう)さん に聞こえたりします。
こうした「言葉の聞き間違い」が頻繁に起こると、 会話が噛みあわなくなったり トラブルの元となったりして
次第に 会話すること自体が 億劫になってしまう可能性があります。
音を選び出す力が弱まる
耳には本来、「聞きたい音を選び出す力」というのが自然と備わっています。
沢山の人がいる場所、賑やかな場所でも 話し相手の声を自然と聞き分けることができる能力です。
しかし、この選別機能も年齢とともに次第に弱まってきます。
すると 賑やかな場所では 話し相手の声を耳が選別することが出来ず、他の大きな音だけを聞き取ってしまい
肝心の相手の話はさっぱり聞き取れない・・・という事になってしまいます。